【第84回】みちびと紀行~鎌倉街道を往く(トカイナカ) みちびと紀行 【第84回】
 丘陵地帯に入っていく
丘陵地帯に入っていく きれいに耕された農地
きれいに耕された農地 美しい自然が残る道
美しい自然が残る道丘陵地帯を街道が続いていく。
あたりはすっかり、里山の風景になった。
これから種まきが始まるのだろうか。
きれいに耕された谷地の農園が、周囲の自然に調和して、優しく、懐かしい景観を作り出している。
 蛇行しながら続いていく
蛇行しながら続いていく 笛吹峠に着いた
笛吹峠に着いたゆるやかな坂道を登り切ると、笛吹峠に出た。
ここから先は、行政区が嵐山町から鳩山町へと変わる。
「笛吹」の名は、正平7(1352)年、南朝方の新田義貞の子・義宗が宗良親王を奉じてここに陣を敷き、足利軍と戦った際に、親王が月明かりの陣営内で笛を吹いたことに由来するとのこと。
その笛の音は、土地の名にとどめるほどに、さぞかし心に響いたのだろう。
たとえ戦場でも、いや戦場であればこそ、ほんのひととき心をなだめる音楽は、きっと必要なのだ。
ずっと時を遡った奈良時代、このあたりは窯業の中心地として栄えていたらしい。
この先、鎌倉街道を南下したところにある武蔵国分寺の瓦は、その大部分がここで生産されたという。
鎌倉街道は、鎌倉時代よりもずっと昔からあった道をベースに整備されていたのだ。
 昔の街道は、鳩山中学校の敷地内を通っていた
昔の街道は、鳩山中学校の敷地内を通っていた敷地内にかつて鎌倉街道が通っていたという鳩山中学を過ぎて進んでいく。
時刻は11:05am、坂の上から自転車に乗って、懐かしい男が現れた。
社会人大学の学友、見山公一さんだ。
今日は、彼の農園で昼ご飯を食べる約束をしていたのだ。
 見山さん登場、ピンクは彼のトレードカラー
見山さん登場、ピンクは彼のトレードカラー見山さんは僕よりも年下で、断然落ち着いているので、彼のことは「さん」付けで呼んでいる。
鎌倉街道から少し外れた「鳩山ニュータウン」に18年来住む、企業のコンサルタント。
職場は都心で、2時間の電車通勤は座っていけるそうだ。
都会からほどよく離れた便利な田舎暮らしを、見山さんは気に入っている。
「『トカイナカ』っていうんですよ。」
5年前に彼から聞いて、この言葉を初めて知った。
もともと都会人でもなく、かと言って田舎に籠もる生活にもなじめそうにない僕にとって、この言葉は魅力的な響きを持つ。
 藪や倒木を片付けて切り拓いた「SORAファーム」
藪や倒木を片付けて切り拓いた「SORAファーム」 シイタケ栽培にも挑戦
シイタケ栽培にも挑戦5年前、彼は、近所の見晴らしのよい雑木林の丘で農園づくりを始めた。
その名も「SORAファーム」。
最初は、植物好きの息子さんのために、自宅の庭の一画を畑にしたのがきっかけだった。
それが高じて、いつの間にか自身の方が畑づくりにのめり込み、本格的に農園をつくろうと、周辺に土地を求めて探し回った。
「灯台下暗し」、それは自宅から徒歩10分の場所に見つかった。
竹藪が生い茂り、倒木が放置された鬱蒼とした雑木林の丘を切り拓き、地域の人々がやってきてほっと一息つける、森の中に公園のような農園をつくる。そんな構想を抱いた。
そうと決まったら、彼の行動は速い。
「あの土地はどなたのものなんですかね。」
周辺の住民に聞き込みをしてまわった。
ようやく見つけた地主さんは、この丘を挟んでニュータウンの反対側、田園風景の中の父祖伝来の土地に住む人物だった。
さっそく訪ねて行き、あらかじめ作っていた「事業構想計画書」を渡して、みごとに土地の使用許諾を得ることができた。
「何が良かったんですかね。かなり謎の人物だと思われたんじゃないですかね、当初は。でも、熱意みたいなものは汲み取っていただけたんじゃないかな。それに町のためになること、人の役に立つことだと思ってくれたのが大きいと思いますね。」
 菖蒲とホタルと紅葉が楽しめる公園づくり
菖蒲とホタルと紅葉が楽しめる公園づくり「SORAファーム」の丘から下りて、その地主さんに会いに行く。
見山さんとはもう随分気心の知れた仲のようで、息子のように可愛がっている様子だ。
「俺の土地も見ていかないか。」
と、連れて行かれた場所は、丘の下の谷地だった。
「このあたり、蛍がいるんだよ。だから菖蒲を植えたよ。土を入れ替えて。あの向こうには紅葉を植えた。いつか、ここに人が訪れて、きれいな風景が見れるようにな。」
そう言いながら、じっとその場所を見つめている。
他に何かやり残したことはないだろうか。
そう思っているかのようだった。
「大事になさっている土地なんですね。」
感じたままのことを伝えると、
「ああそうだ。ご先祖様から受け継いだ土地だからね。」
視線の先をずっと谷地の風景に向けたまま、つぶやくように答える。
それは、自分自身に向けた言葉でもあるかのように、力強く響いた。
 SORAファームで昼食
SORAファームで昼食再びSORAファームに戻り、昼食をとった。
見山さんが農協で買ってきてくれたお弁当と「鳩山まんじゅう」をご馳走になる。
それぞれの美味しさに加えて、里山の景観と澄んだ空気が、最高の食事を演出する。
ベンチに座って見渡す眺めは、荒れ放題の竹藪を彼が少しずつ切り拓いて出現したものだ。
真剣にコーヒーを淹れる彼を横目に思った。
もっと早くここに来ればよかった。
ここに来て、見山さんのことがずっとよくわかったように思う。
人を理解するには、その人の好きなものを知るのが一番だ。
 とう立ち菜を収穫
とう立ち菜を収穫 妻に調理してもらった。妻曰く「湯がき過ぎた。」
妻に調理してもらった。妻曰く「湯がき過ぎた。」「これ持って行ってください。この辺の人はよく食べるみたいなんですよ。」
菜の花のように見えたそれは、収穫せずにそのままにしていた白菜から、にょきっと伸びた薹(とう)だった。
「とう立ち菜」と呼ばれるもので、市場には出回らない農家が食べる野菜ということだ。
そんな貴重な野菜をもらうのはわるいと言うと、
「いえ、一日経つと別の薹がもう伸びてるんですよ。毎日採ってもすぐに生えてきますから。」
と、その場でごっそり収穫したものをもらった。
「湯がいて醤油とごま油かけると美味いですよ。」
家に帰って調理したそれは、野生の甘みがあって絶品だった。
 おしゃもじ山展望台に行った
おしゃもじ山展望台に行った 展望台の上に立つ見山さん
展望台の上に立つ見山さん時刻は3:30pm。
今日のゴールは、東武越生線の西大家駅。
そろそろ出発しようと腰を上げると、
「僕も一緒に歩きます」と、西大家駅まで見山さんが同伴することになった。
彼とは以前、中山道の一部区間を一緒に歩いたことがある。
足に故障を抱えていて長距離は歩けないというので、無理をせず一部区間だけ。
それでも、目にするものにいちいち興味を示して、それが僕にとってはすこぶる楽しかった。
おかげで、一人で歩いていたら見過ごしたはずのものを発見できた。
今日はどんな気づきをもらえるだろうか。
今宿交差点のそばにある「おしゃもじ山」に登って、西大家駅の方向を確かめた。
雲がわき風が吹いてきたけれど、天気はもちそうだ。
 森の中の延慶板碑
森の中の延慶板碑 毛呂山町歴史民俗資料館に立ち寄った
毛呂山町歴史民俗資料館に立ち寄った 鎌倉街道掘割の遺構
鎌倉街道掘割の遺構越辺川(おっぺがわ)を渡って毛呂山町に入った。
「大類グラウンド」から先、「毛呂山町歴史民俗資料館」の辺り一帯には、鎌倉街道の遺構が残っている。
森の中の小径には、「延慶板碑」と呼ばれる謎の石碑が、古代のオベリスクのように静かに佇んでいた。
よくこの辺りを車で通るという見山さんも、この場所は初めて知ったそうだ。
つい最近、政府の文化審議会は、この辺りの鎌倉街道・上道の遺構を史跡に指定するよう、文科省に答申した。
この道が歴史的価値を認められることもそうだが、実際に歩いて街道をたどる人が増えれば、なお嬉しいことだ。
 街道が続いていく
街道が続いていく 東京国際大学坂戸キャンパスの中を歩く
東京国際大学坂戸キャンパスの中を歩く 学生が駅に向かっていく
学生が駅に向かっていく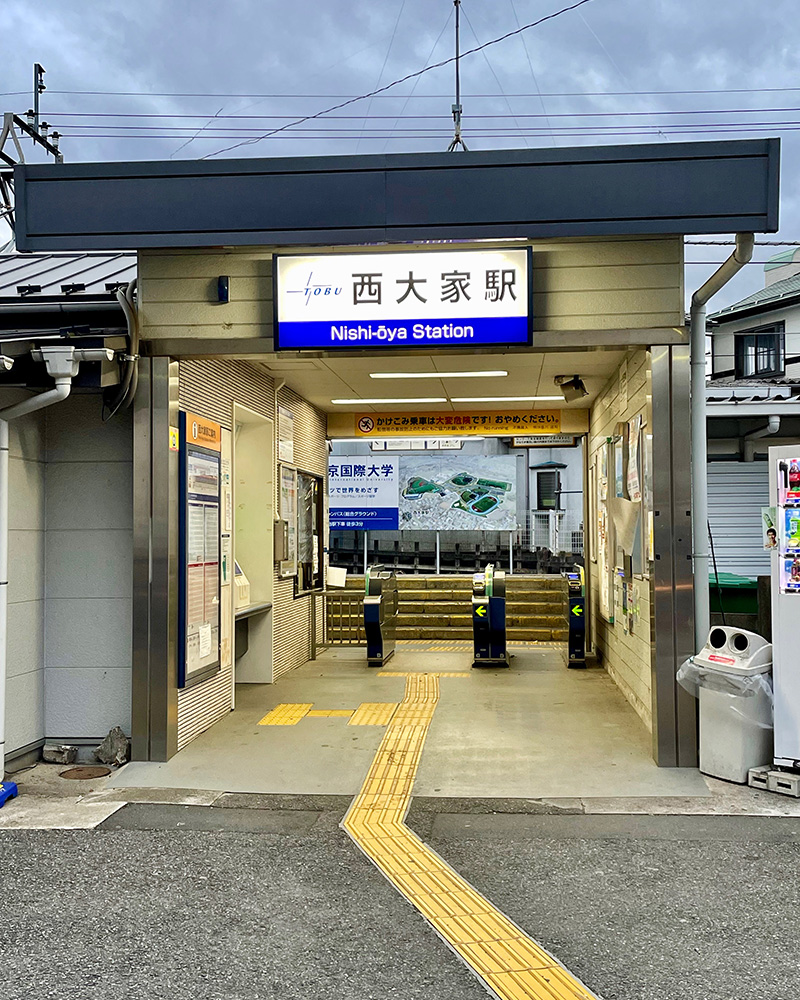 今日のゴール、西大谷駅
今日のゴール、西大谷駅高麗川(こまがわ)を渡り、東京国際大学の坂戸キャンパスの中を歩いていく。
今日の講義は終了したらしく、帰宅する学生が最寄りの西大家駅へと向かっていく。
時刻は5:45pm。
見山さんとも、そろそろ駅でお別れだ。
僕が愛してやまない「街道歩き」に付き合ってくれた友に心から感謝する。
武蔵嵐山駅からここまで4万歩、距離にして30.6km。
「トカイナカ」の自然と生活を垣間見ることができた。
最近はリモートワークのブームもあり、「自然に囲まれた生活」と、その良さをアピールしている地域も多い。
けれど、僕が魅力を感じる場所は、「手付かずの自然」などではなく、人の手が入った自然、汗水垂らして作り上げた里山の景観、人の暮らし、温もりのある生活空間なのだと、今回歩いて実感した。
トカイナカ、なかなか魅力的じゃないか。
さあ、家に帰って、妻に「とう立ち菜」を調理してもらおうか。
都心まで約1時間、空腹も我慢できそうなほどに、電車はスピードを上げてビルの街へと駆け抜けていった。

