【第77回】みちびと紀行~鎌倉街道を往く(古墳の里) みちびと紀行 【第77回】
 遠くの山に高崎観音が見える
遠くの山に高崎観音が見える烏川に架かる一本松橋を渡っていく。
遠くの山に、米粒のように高崎観音が立っている。
鎌倉街道は、高崎商科大学のキャンパスの先で、車通りの激しい県道となり、わきに追いやられた道祖神と石仏だけが、昔の面影を残していた。
 県道わきの石仏たち
県道わきの石仏たち街道沿いのそば屋で昼食をとる。
作業着姿の人で繁盛する店では、一段落ついた店主が、客と一緒に頭上のテレビを見ていた。
ウクライナで起こっている戦争のニュースだ。
「小麦粉の値段、大丈夫?」
「どうかねぇ。北海道産使ってるんだけどね。」
世界の11%の小麦を産出するというウクライナ。
常連らしき客と店主の邪気のない会話の中で、様々な距離感が錯綜する。
戦場となっているウクライナへの地理的な遠さ。
戦争という現実への心理的な遠さ。
そして、小麦粉の値段に対する身近な関心。
「平和な」国のテレビ番組は、戦争の話題は扱い慣れないようで、連発する「平和」という言葉が、ただただむなしく流れていた。
 高さ1.5mの山上地蔵尊
高さ1.5mの山上地蔵尊 上野三碑ののぼりが至るところにあった
上野三碑ののぼりが至るところにあった 3つの石碑と最寄駅を無料バスが巡回している
3つの石碑と最寄駅を無料バスが巡回している県道から外れて坂道を登り、「山の上地蔵尊」にたどり着く。
この辺りは、かつて山本宿と呼ばれて賑やかだったそうだ。
街道を行く人びとが立ち止まり、この地蔵尊とその周りに集う石仏たちに向かって祈っていた。
そんなことを、ひっそりとした辻に立って想像してみる。
ふと周りを見ると、「上野三碑(こうずけさんぴ)」のひとつ、「山上碑(やまのうえひ)」の案内板が、これでもかと言わんばかりに田舎の風景に映りこんでいる。
ユネスコの「世界の記憶」にこの石碑が登録されたことで、観光資源として売り出そうというのだろう。
そのアピールに応じて、すこし寄り道をすることにした。
 山の上古墳
山の上古墳山上碑は、その名の通り山の上にあった。
長く急な階段を登りきると、石室のある古墳が現れる。
その隣には、堅牢な小屋の中に、山上碑が大切に守られていた。
紀元681年、天武天皇の御代に作られたもので、完全な形で残る石碑としては、日本最古のものということだ。
そう言われてみると、この石の形、刻まれた文字が、不思議な力を持った尊いものに思えてくる。
 日本最古の石碑
日本最古の石碑日本には、そもそも石碑を建てる文化はなかった。
山上碑が新羅の石碑に似ていることから、この地域には、朝鮮半島からの渡来人が住んでいたと考えられるそうだ。
石碑に文字を刻むことも、それに適した自然石を探すことも、結構な苦労を要するはずだから、刻まれた文章の内容も、なにかとても大切なことなのだろう。
石碑を建てた人は、後世にいったい何を伝えようとしたのか。
そんなことを思いながら説明板を見ると、この石碑は、山上古墳に埋葬された黒売刀持(くろめとじ)という女性の追善供養のために、息子の長利という僧が建てたものだった。
碑文の中身を現代語訳すると、次のようになる。
肩の力が抜けた。
なんと、母親の供養のためというよりも、自分の系譜をこと細かく説明する碑文だったのだ。
いや、好意的に解釈するならば、「今ここにいる私は、あなたとそのご先祖さまがいなければ、存在できなかったのです。あなたたちから生まれた子孫は、このように石碑を建てられるほどに、つつがなく暮らしていますよ。」と言いたかったのかもしれない。
よくよく考えてみれば、近所にあるお寺の墓石も、そもそもの趣旨は変わらなかったのではないか。
日本最古の石碑は、なにか大事業を成し遂げたとか、戦績を誇るということでなく、一個人のご先祖様の系譜を刻んだものだった。
子孫にバトンをつないでいくことこそが、最大の事業であるかのように。
そのことが、このぽかぽかとした春の陽気とあわせて、なんとも穏やかな気持ちにさせた。
 長い階段を降りていく
長い階段を降りていく 山名八幡宮では記念写真の真っ最中
山名八幡宮では記念写真の真っ最中 鎌倉街道は右方向へ
鎌倉街道は右方向へ 山名5号墳と山名61号墳
山名5号墳と山名61号墳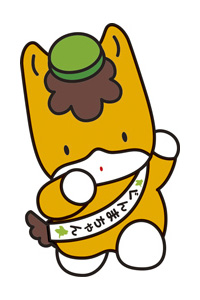
群馬県のゆるキャラ「ぐんまちゃん」
山上古墳から山名八幡宮まで田舎道を通り、再び鎌倉街道に沿って歩いていく。
この辺り、鏑川(かぶらがわ)を渡って藤岡市に至る一帯は、鎌倉街道沿いで最も古墳が多いところだ。
群馬県には1万3千基もの古墳があり、東日本最大の古墳大国と言われている。
そのような大きな勢力が、なぜこの地域にあったのだろうか。
調べてみると、おもしろいことが分かってきた。
この地は、「群馬」の名の通り、馬と深いつながりがあったのだ。
 鏑川を渡って藤岡市へ
鏑川を渡って藤岡市へ5世紀中頃、この地域に、朝鮮半島からの渡来人が移り住んだ。
おそらく、ヤマト政権によってこの地へ招聘されたということだろう。
目当ては「馬」だ。
彼らの持つ馬の飼育技術、馬具の生産技術が、どうしても欲しかった。
馬は当時、輸送手段や、農耕・土木作業用として重宝されていて、軍事など危急の際には、その活用が期待されていた。
かつて「毛野(けの)」と呼ばれたこの地域は、当時の幹線道路「東山道」に沿った物流の拠点で、しかも東北地方の蝦夷に対する前線基地でもあった。
ヤマト政権は、この地域に「御牧(みまき)」と呼ばれる官営牧場を9つ置き、馬の飼育を盛んに行う。
多くの河川が流れるこの一帯の河岸段丘は、馬の放牧地、水のみ場として適していた。
鎌倉時代を担った東国武士団の祖先たちは、こうした、馬が身近にいる環境で生まれ、その文化・気風を育んできたのだ。
 街道がうねりながら続いていく
街道がうねりながら続いていく 伊勢塚古墳の石室にはきれいな模様があった
伊勢塚古墳の石室にはきれいな模様があった 伊勢塚古墳
伊勢塚古墳古墳群を縫うように、鎌倉街道が続いていく。
次から次へと出現する古墳の丘は、春先の風景にマッチしていた。
草原で鬼ごっこしたり、石室に入ってかくれんぼしたり、きっとこの辺りの子どもたちは古墳を遊び場にしてきたことだろう。
 東日本最大級という七輿山古墳
東日本最大級という七輿山古墳 古墳群を縫うように鎌倉街道が通る
古墳群を縫うように鎌倉街道が通る 藤岡歴史館に寄った
藤岡歴史館に寄った鎌倉街道沿いに「藤岡歴史館」があったので、寄ってみる。
中に入ると、古墳からの出土品がずらりと展示されていた。
おや?これは・・・。
館内の一画に、古墳と関係があるのかないのか、零式戦闘機の開発者、堀越二郎の展示があった。
宮崎駿のアニメ映画「風立ちぬ」のモデルとなった人物だ。
どうやら、彼はこの辺りで生まれ、子ども時代を過ごしたようだ。
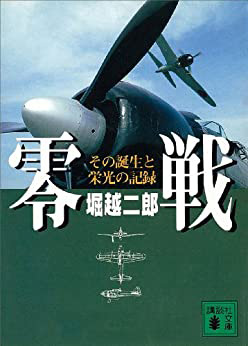
堀越二郎著「零戦」
堀越二郎が生まれたのは1903年、ライト兄弟が初飛行に成功した年だ。
「飛行少年」という雑誌を夢中に読む少年で、東京帝国大学航空工学科に入学して以降は、ひたすら飛行機づくりに没頭する。
そしてついに、あの「零戦」を世に送り出すのだ。
零戦が先の大戦に与えたインパクトについて、ここで詳細は語らない。
けれど、彼の著した「零戦」という本を読めば、零戦の開発現場も、戦争のはじめから終わりまで、死にものぐるいの戦場だったことがよく分かる。
当時の資源も時間も人員も限られていた日本で、それまでの世界の戦闘機をはるかにしのぐものを作り出せたのは、明けても暮れても課題を追い続ける、彼をはじめとした技術者たちの鬼気迫るほどの執念にほかならない。
著書の中で、彼はこう語っている。
日本は敗戦し、その後戦闘機の開発をすることはなかった。
けれど、堀越二郎の技術者魂は、戦後の日本の復興の中で、確実に引き継がれていったにちがいない。
 堀越二郎はこんな景色を見ていたのか
堀越二郎はこんな景色を見ていたのか世界に冠たる飛行機を作り出した人物は、この古墳群の景色を見ながら育ったのだな。
藤岡歴史館を出たあとは、そんなことを思いながら街道を歩いた。
たしか、ライト兄弟の初飛行の年に、堀越二郎が生まれたと言ってたな。
と思い出し、ライト兄弟についてスマホで調べてみる。
・・・息をのんだ。
スマホの画面には、まさに目の前に広がる風景が映っていたのだ。
いや、正しくは、米国ノースカロライナ州・キルデビルヒルズにある、ライト兄弟の初飛行を記念して建てられたメモリアルの画像だった。
 ライト兄弟メモリアル(出典:産経フォト)
ライト兄弟メモリアル(出典:産経フォト)古墳のようなこんもりした丘を前にする、ライト兄弟のモニュメント。
 白石稲荷山古墳の上から景色を眺める
白石稲荷山古墳の上から景色を眺める彼らと堀越二郎が、時空を超えてここに立っている。
そんな錯覚を覚えながら、古墳の丘に登り、空を眺めていた。

