【第69回】みちびと紀行~下田街道を往く(天城越え) みちびと紀行 【第69回】
 全長446m、現存する石造トンネルでは国内最長
全長446m、現存する石造トンネルでは国内最長天城山隧道(旧天城トンネル)を歩いていく。
長さ446メートル、幅と高さが3.5メートル。
ぽつりぽつりと距離を置いて続くランプの灯は、暗闇を遠ざけはするものの、静寂の中を独り歩くにはいまだ心細い。
景気づけに、頭の中で、石川さゆりが「天城越え」を熱唱していた。
 天城湯ケ島の側に出た。公衆トイレと小さな駐車場がある。
天城湯ケ島の側に出た。公衆トイレと小さな駐車場がある。「天城山」というのは連山の総称で、伊豆半島の南北を屏風のように隔てている。
かなりの難所だったようで、道が険阻なうえに崩落も頻繁にあり、下田街道のルートが何度も変更された。
明治38(1905)年に、悲願のトンネルができるずっと前、幕末の頃は、「天城越え」というと、ここより西にある二本杉峠を越えていったらしい。
下田から駕籠に乗って江戸に向かったハリスとその一行も、二本杉峠を越えていった。
ハリスの手記には「道は往々にして35度の角度をなし」と記され、いかに危ない道だったか強調されているから、相当肝を冷やしたことだろう。
 江藤延男追慕之碑
江藤延男追慕之碑トンネルを抜けると、「江藤延男追慕之碑」があった。
双眼鏡を手にしたこの人物は、天城山での遭難者救助のために、昭和38年に設立された「天城を守る会」の初代会長ということだ。
天城山中では、昭和32 (1957) 年12月、満州国皇帝溥儀の姪で学習院大学2年に在籍していた愛新覚羅慧生(あいしんかくらえいせい)と、同級生大久保武道が、ピストル自殺を遂げた事件が起こった。
このことが、「天城山心中」、「天国に結ぶ恋」とマスコミに騒がれたことで、会の発足当時は、天城山にやってきて自殺する男女が多く、その捜索活動もしていたらしい。
「天城越え」が命がけの恋の歌なら、この場所はまさにその舞台となったわけだ。
 川が北に向かって流れていく
川が北に向かって流れていく踊り子歩道は、天城大橋のあたりで国道414号を横切り、再び渓谷沿いの道となる。
川の流れの方向が変わり、天城峠が分水嶺だということを実感する。
狩野川はここを源流として北上し、沼津で海に出る。
ここから先、下田街道は、この狩野川に沿って続いていく。
 このあたりに炭焼き市兵衛の墓がある
このあたりに炭焼き市兵衛の墓がある 炭焼き市兵衛の墓
炭焼き市兵衛の墓林を抜けると、「炭焼き市兵衛の墓」が現れた。
宝歴・明和年間(1751〜72年)のころ、紀州の尾鷲からやってきて、伊豆に炭焼きの新しい技法を伝えたとされる人物だ。
天城の炭は「伊豆備長」としてよく知られ、江戸城の「本丸・西丸御風呂屋御用炭」にもなった。
幕府は、天城の森林を厳重に管理し、天城山御林地の村々には炭を焼く権利を与える代わりに、杉や檜の苗木を植え付けさせたという。
森林資源を効率の良いエネルギーに転換できる炭焼きは、この天城で成立した模範的な産業だったのだ。
そして、この他所から来た「無名の」技術者の功績が、その産業の下地にある。
 道の駅天城越えの敷地内
道の駅天城越えの敷地内時刻は2:20pm、そういえばお腹がすいた。
踊り子歩道沿いに道の駅があったので寄ることにした。
「道の駅天城越え」。
地名ではなく、天城を越えるという「行為」を名前にしているところがユニークだ。
「天城越え」はそれほどまでに大衆ウケする言葉になったのだろう。
食堂は、ラストオーダーの時間ぎりぎりで、早く調理できそうな猪肉のカレーライスを注文した。
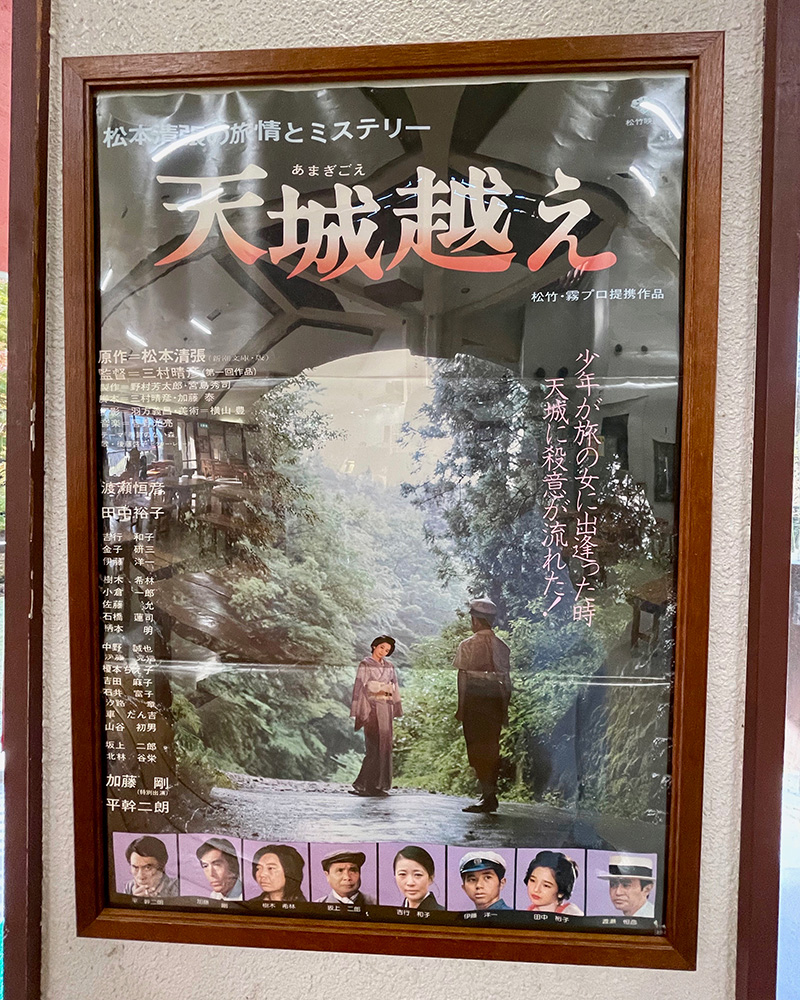 映画「天城越え」のポスターがあった
映画「天城越え」のポスターがあった食堂の壁には、天城にちなんだ映画のポスターが3枚。
少年期を天城で過ごした井上靖。
彼の自伝的小説を映画化した「わが母の記」。
山口百恵主演の「伊豆の踊り子」。
そして1983年に公開されたミステリー映画「天城越え」。
僕の中で「天城越え」といえば、石川さゆりの歌よりも先に、その題名の映画で記憶されていた。
大正10年に、上狩野村(今の天城湯ヶ島町)で実際に起こった「御料地内土工殺人事件」を題材に、松本清張が書いたミステリーを映画化したものだ。
娼婦役で主演した田中裕子の渾身の演技が、まだ若かった僕の記憶に強烈に残っている。
情念あふれるストーリーに、天城の風景はぴったりとはまっていた。
雨のシーンが多かったように思う。
 いよいよ踊り子歩道の終点だ
いよいよ踊り子歩道の終点だ今晩の宿は修善寺にとってある。
あとどれくらい歩くのだろうか。
食後のお茶を飲みながら調べると、なんと!あと17kmも歩かなければならない。
疲れはないが、途中で確実に日が暮れるだろう。
そもそもここまで来るのに、こんなに時間がかかるとは思っていなかった。
「天城越え」をなめてかかった自分を反省。
あわてて道の駅を出て、早足で歩いていく。
 浄蓮の滝、舞い上がり、揺れ落ちる
浄蓮の滝、舞い上がり、揺れ落ちる踊り子歩道の終点、浄蓮の滝に着いた。
気持ちは急いでいたけれど、この滝だけは見ておきたい。
滝壺までの急な坂道をずんずん下っていくと、25メートルの落差を流れ落ちる神秘的な滝が現れた。
 滝壺の脇に天城越えの碑があった
滝壺の脇に天城越えの碑があった滝壺の脇には、「天城越え」の歌碑がある。
1986年、バブル絶頂期のころ、この歌は世に出た。
作詞、吉岡治。作曲、弦哲也。
制作に当たって両氏は、この地で合宿し、周辺を歩き回ったそうだ。
弦氏によれば、当初吉岡氏は「歌詞の中に地名を入れたくない」と言っていたらしい。
けれど、現地入りすると考えが変わり、「どうしても地名を入れたくなった」と語ったとのことだ。
その心境は僕も歩いてみて分かるような気がした。
歩きながら目に入る情景のことごとくが、天城にとって必然で、あの歌の心理を描写しているように思えたからだ。
11月中旬は、南国の伊豆ではまだ時期的に早いのか、「山が燃える」というほどの紅葉には巡り会わなかったけれど。
浄蓮の滝、天城隧道、寒天橋・・・。
これらの地名は天城の歌枕として、この先ますます定着していくことだろう。
 天城遊歩道が湯ヶ島温泉まで続く
天城遊歩道が湯ヶ島温泉まで続く 静かで美しい道
静かで美しい道 透き通る川を渡る
透き通る川を渡る浄蓮の滝から先は、「踊り子歩道」に代わって「天城遊歩道」が、湯ヶ島温泉までの道を示してくれる。
透き通る川に沿って30分、山間の静かな温泉地、湯ヶ島温泉にたどり着いた。
 湯ヶ島温泉に着いた
湯ヶ島温泉に着いた 島崎藤村が逗留した落合楼
島崎藤村が逗留した落合楼島崎藤村、梶井基次郎、川端康成・・・。
文豪たちがこの地に惚れ込み、何度となく滞在した。
中でも、伊豆じゅうの温泉場を渡り歩いた川端は、とりわけ湯ヶ島を愛し、彼が初めて伊豆を旅した、二十歳のころの「伊豆の踊り子の旅」以来、何度もこの地を訪れている。
賑やかな温泉場を避ける傾向があったようで、「湯ヶ島での思ひ出」では、この地がいかに「物寂びた所」であるかを愛おしむかのように語り、それを承知でここに来ていると記している。
 川端康成の定宿、湯本館
川端康成の定宿、湯本館湯本館があった。
川端康成の定宿で、「伊豆の踊り子」はここで執筆された。
梶井基次郎も昭和元年の暮れからここに逗留し、「伊豆の踊り子」の校正を「静かに、注意深く、楽しげに」手伝ったらしい。
多くの文豪たちがしばしば旅先で執筆するのには、どういったわけがあるのだろうか。
川端は次のように説明していた。
コロナ禍でリモートワークが注目されているけれど、作家のようにクリエイティブな仕事は、昔から旅先の環境を必要としていたのだ。
 日が暮れてきた
日が暮れてきた 山の向こうに日が落ちてしまった
山の向こうに日が落ちてしまった日が暮れていく。
こうなったら腹をくくって、焦らずに歩いていこう。
安全のために、50メートル先まで照射できる懐中電灯をリュックから取り出して、自分の存在をアピールしながら歩いていく。
 修善寺の街に着いた
修善寺の街に着いた 独鈷の湯
独鈷の湯 修善寺の山門
修善寺の山門 竹林の細道
竹林の細道 今宵の宿、ゲストハウスHostel Knot
今宵の宿、ゲストハウスHostel Knot6:30pm、修善寺の街に着いた。
暗がりの道から解放されて、暖かな街の明かりが僕を癒した。
街の中心にある修善寺の山門や独鈷の湯、そして細道までもがライトアップされていて、温泉地の雰囲気を盛り上げている。
今晩の宿「ゲストハウスHostel Knot」の灯を見つけ、スタッフの笑顔に迎えられると、全身の緊張が一気に解けた。
梨本の「天城温泉・禅の湯」からここまで10時間、歩数47,000歩、距離にして36kmの歩き旅だった。
荷をほどき、宿と提携している近くの民宿で、修善寺の温泉に浸かる。
今日、「天城越え」というちょっとした冒険を完遂した。
その充実感を、露天風呂で月を眺めながら味わっていた。

